目次
はじめに:なぜ「お問い合わせ対応」をLINEに集約すべきか
企業と顧客の接点は年々多様化しています。電話やメール、Webフォームに加えて、SNSやチャットアプリでの問い合わせが当たり前になったいま、「顧客が一番使いやすい場所で、最短で答えを得られるかどうか」が満足度を左右する大きな要因となっています。
中でも圧倒的な存在感を放っているのがLINEです。日本国内での利用率は9割を超え、1日に十数回以上アプリを開く生活インフラ。顧客が何か疑問を持った瞬間に自然とアクセスできる場所こそ、問い合わせ対応の理想的なチャネルといえるでしょう。
本記事では、
- LINEでのお問い合わせ対応を最適化するための3つの視点、
- 2025年に押さえるべきカスタマーサポートの最新トレンド、
- 無料機能から高度化までの進化パス、
- 実際に成果を上げている成功事例
を体系的に解説していきます。無料で使える基本機能からAIやデータ連携を活用した高度な仕組みを網羅する、LINE公式アカウントを「単なる問い合わせ窓口」から「顧客体験を生み出すプラットフォーム」へと進化させる実践的な方法を知りたい方におすすめの記事です。
お問い合わせ対応システムを選ぶ前に考える3つの視点
「LINEでお問い合わせ対応を始めたいが、何から考えるべきか分からない」——そんな声をよく耳にします。
LINEを顧客対応に活用する際、ただ機能を導入するだけでは十分ではありません。大切なのは「どう設計すれば効率化と満足度を両立できるか」という視点です。ここでは、システム選定で失敗しないために押さえるべき3つの判断基準を解説します。導入後に「こんなはずじゃなかった」とならないよう、まずは全体像を把握しましょう。
① 一対多対応:自動化と拡張性
問い合わせ対応の基本は「行ったり来たりのやり取りの数を減らす」こと。LINE公式アカウントが標準提供する一律応答メッセージやキーワード応答を組み合わせれば、営業時間外やよくある質問に即座に回答できます。さらにリッチメニューを活用すれば、顧客が自ら答えを見つける“セルフサービス”環境を構築可能です。

[LINE自動返信の設定方法]
1. LINE公式アカウントの作成
・LINE公式サイトでLINE公式アカウントに登録します。
アカウント作成後、管理画面(LINE Official Account Manager)にログインします。
LINE公式アカウント開設前の方にはこちらの記事がおすすめです: LINE公式アカウントを始める前に知っておきたい!ポイント5つ
2.自動返信メッセージの設定
・メニューから「応答設定」を選択します。
「自動応答メッセージ」を選びます。
・自動応答メッセージの作成:
「自動応答メッセージ」の設定画面で、「自動応答メッセージを設定する」を選択します。
メッセージの種類(例:あいさつメッセージ、応答メッセージなど)を選び、メッセージ内容を入力します。
3. キーワード応答メッセージの設定
キーワードに対して特定のメッセージを送る設定も可能です。
「キーワード応答メッセージ」を選択し、特定のキーワードとそのキーワードが含まれたメッセージに対する応答内容を設定します。
>こうした自動化設計は、単に工数を削減するだけでなく、ブロック率を下げる効果も期待できます。顧客が「聞いても返事が遅い」と感じる前に即応できるからです。一対多の効率化と、一人ひとりへの配慮を両立させることが、最初のステップとなります。
※一律応答・キーワード応答の選び方や注意点の解説はこちら>LINE自動応答 設定方法と注意点を導入事例とともに紹介!
※LINEチャットボットの詳しい作成方法はこちら>初心者でも簡単!LINEチャットボットで顧客対応を完全自動化
しかし、自動化だけでは限界があるのも事実。問い合わせが複雑化したり、専門的な対応が必要になったりした場合、人的リソースをどう配分するかが次の課題となります。
② 多対一対応:チーム協働と担当振り分け

LINE経由の問い合わせが増えると、複数のスタッフで協働する体制が不可欠になります。しかし、適切な権限管理がなければ「複数人が同じ顧客に返信して混乱」「引き継ぎが曖昧で顧客に何度も同じ説明を求める」といった問題が発生します。
たとえば、こんな課題はありませんか?
① アカウント切り替えの手間
- 店舗ごと、部門ごとにLINE公式アカウントを運用
- 管理画面を何度もログイン・ログアウト
- 対応が遅れ、顧客満足度が低下
② 情報共有と一貫性の欠如
- 「前回のやり取り」が別アカウントで確認できない
- 顧客が同じ説明を繰り返す必要
- 「話が通じていない」不信感
③ 権限管理の不十分さ
- 全スタッフが全情報にアクセス→セキュリティリスク
- 役割分担が不明確→対応の混乱
これらの課題解決に役立つのがクレッシェンドラボ・CAACによる自動アサイン機能です。顧客からのメッセージに含まれるキーワードを検知して、最適な担当者に振り分けることが可能になり、応答スピードと専門性を向上できます。「誰が対応するのか」を明確にする仕組みを導入することが、チーム全体の信頼性を高める鍵となります。
LINEお問い合わせ対応で、CAACは以下の点で活躍:
- キーワードやQRコードをもとに自動で専門担当者へ振り分け
- 複数のアカウントを一画面で管理
- 担当者やチームごとに5段階の閲覧権限を管理
- メッセージ履歴の統合でチーム間のスムーズな情報共有
効率的なチーム体制が整ったら、次に考えるべきは「長期的な視点」です。今の課題を解決するだけでなく、将来の成長にも対応できる柔軟性が必要になります。
③ 将来性:低コストDXとAI活用
カスタマーサポートを“今の課題解決”だけで選んでしまうと、数年後には再構築が必要になることも少なくありません。そこで注目すべきがAPIによる拡張性と、AIとの親和性です。
LINEはMessaging APIを通じて、CRMやCDP、ECサイト、GAなど幅広い外部ツールと連携できます。これにより、問い合わせ対応の枠を超えて、マーケティングやLTV向上施策へとシームレスに発展させられるのです。
さらに、AIによる自動応答の高度化や顧客体験のパーソナライズは今後ますます必須となるでしょう。低コストでスタートし、将来のDXにスムーズに接続できる基盤を作ることこそが、長期的に見た“賢い投資”と言えます。
LINEでお問い合わせ対応を行うメリット
LINEを顧客対応のチャネルに選ぶことは、単に便利だからではありません。実際に運用してみると、メールや電話とはまったく異なる強みが見えてきます。ここでは、LINEという媒体の人気度を超えた2つの大きなメリットをマーケティングの視点から整理してみましょう。
① 親密性:1対1のプライベート感
LINEの強みは、単なるチャットツールを超えた“個人的なつながり感”にあります。顧客からすれば、企業と話しているというよりも、友人に連絡するのと同じ感覚で相談できるのです。
この距離感は、問い合わせ対応を「トラブル解決の場」から「顧客体験を育む接点」へと変えてくれるチャンスももたらします。1対1でのやり取りを通じて、「自分の声を聞いてくれるブランド」という信頼を育むことによって、結果的にロイヤリティ向上へと直結していきます。
② データ連携:CRM/CDPとの統合
LINEでのやり取りは、そのまま顧客データの宝庫です。タグ付けや属性情報を活用することで、問い合わせ履歴や購買行動を可視化し、CRMやCDPと連携させれば、より精度の高いマーケティングに展開できます。
例えば、商品に関する問い合わせをした顧客にだけ関連情報を配信したり、FAQを見た顧客をリターゲティングしたり。「お問い合わせ対応」を起点に、次の購買体験やLTV向上へつなげられるのは、LINEならではの強みです。
この2つのメリットが示すのは、LINEお問い合わせ対応が単なる「効率化ツール」ではなく、顧客との関係性を根本から変える戦略的資産だということです。 従来のメールや電話は「問題が起きたときだけ使う窓口」でした。しかしLINEは、問い合わせ対応を通じて顧客との日常的な接点を生み出し、そこから得られるデータを次の顧客体験向上に活かせる——つまり、問い合わせ対応が終わりではなく、長期的な関係構築の始まりになります。
LINE公式アカウントでお問い合わせ対応の種類と選び方
LINEでお問い合わせ対応を始める際、ビジネスの規模や問い合わせの複雑さに応じて、最適な方法は異なります。
方法1:完全自動応答
特徴: 人の手を介さず、すべて自動で返信
おすすめ:
- 問い合わせがパターン化(営業時間、駐車場など)
- 24時間対応を低コストで実現したい
- 小規模事業者
メリット: 24時間対応、人件費ゼロ、即時回答
デメリット: 複雑な対応不可、柔軟性が低い
方法2:完全有人対応
特徴: すべてスタッフが1対1で対応
おすすめ:
- 高額商品・サービス
- 個別相談が必要(不動産、保険など)
- パーソナライズで差別化
メリット: 柔軟対応、信頼関係構築
デメリット: 人件費高、営業時間限定
方法3:ハイブリッド対応(★推奨)
特徴: 自動応答と有人対応を組み合わせ
フロー:
顧客メッセージ
↓
自動判定
├→ FAQ → 自動応答
├→ 営業時間外 → 自動案内
└→ 複雑な質問 → 有人対応
おすすめ: ほとんどの企業
メリット: 効率と満足度の両立、コスト最適化
デメリット: 初期設定に時間
比較表
.png?width=1200&height=627&name=Increase%20LINE%20Repeater%20%20(1).png)
推奨:ほとんどの企業には「ハイブリッド対応」が最適!
無料で使えるLINE公式アカウント機能4選
「LINEでお問い合わせ対応を始めたいけれど、コストが気になる…」という声は少なくありません。実は、LINE公式アカウントには無料で使える標準機能が数多く揃っており、最初の一歩を踏み出すには十分すぎる環境が整っています。ここでは、基本機能の中でも特に“顧客対応に効く”機能をピックアップしてご紹介します。
① 応答メッセージ:営業時間外も安心
問い合わせが来てもすぐに対応できない時間帯は必ず存在します。そんなときに役立つのが応答メッセージです。営業時間外や特定のキーワードに応じて、自動的に返信を設定できます。
例えば、営業時間外には「現在の営業時間は平日9:00〜18:00です。順次対応いたします」という案内を送るだけでも、顧客は安心感を得られます。待たされている不安を軽減するだけで、ブロック率やクレーム率を下げる効果があるのです。
② タグ付けとセグメント配信:顧客理解を深める
顧客一人ひとりにタグを付与し、属性や行動に応じて管理できるのもLINE公式アカウントの強みです。よくある質問を投げかける顧客には「FAQユーザー」タグを、購買履歴のある顧客には「リピーター」タグを、といった具合に整理すれば、次回以降の問い合わせ時にすぐに状況を把握できます。
さらに、このタグを使ってセグメント配信を行えば、「必要な人にだけ適切な情報を届ける」ことが可能になります。これにより、不要な通知によるブロック率を防ぎながら、顧客体験を高めることができます。

LINE公式アカウントの基本的なタグ機能だけでも十分に効果的ですが、「もっと細かく顧客を理解したい」「複数の条件を組み合わせてセグメント配信したい」という場合は、MAACとの連携が威力を発揮します。
例えば:1)「20代女性」×「セール情報重視」×「過去3ヶ月未購入」といった多層的なセグメント
2)クリック行動やアンケート回答を自動でタグ化
3)A4連携による購買履歴・閲覧履歴との統合
このレベルの高精度パーソナライズが必要な場合は、MAACの活用をご検討ください。
▶ MAACとの連携で可能になる高精度パーソナライズ事例はこちら:脱とりあえず一斉配信 LINEでのセグメンテーションをより高度に、効果的に
③ 多様なメッセージ形式:問い合わせを“体験”に変える
LINEでは、テキストだけでなく画像・動画・PDF・クーポン・アンケートなど、多彩な形式で情報を届けられます。たとえば、駐車場の場所を聞かれたら地図付きの画像を即時送信、セールの案内はクーポン付きメッセージで配信、といった活用が可能です。
特にリッチメニューは、FAQや問い合わせ導線を視覚的に整理できるため、顧客が自ら解決できる「セルフサポート機能」として活躍します。“聞く前に解決できる”環境を整えることが、問い合わせ対応の効率化につながるのです。
<導入事例>
LINE標準機能ではリッチメニューは1ページ固定ですが、MAACなら複数ページのリッチメニューを設計可能。例えば、「新商品紹介」「キャンペーン情報」「FAQ」など、用途別にページを分けることで、ユーザーが求める情報をよりスムーズに探せるようになります。
デニムブランドYANUKは、LINE公式アカウントのリッチメニューを活用し、メンズ・ウィメンズそれぞれのユーザーに最適な情報を提供。無料機能に加えて、MAACのタブ切り替え機能を活用することで、1つのリッチメニュー内でターゲットごとに適切なコンテンツを表示し、ユーザーエクスペリエンスを向上させました。
これにより、ブランドに対するエンゲージメントが向上し、オンラインストアへの遷移率が大幅に増加。限られたスペースを最大限に活用しながら、消費者のニーズに応じた情報提供が可能になりました。

インタビュー記事はこちら> 「リッチメニューでも活用の仕方次第で購買までいける!」 YANUK 牧様に聞くMAAC活用のコツ
④ 担当切替と営業時間設定:対応の断絶をなくす
複数スタッフで対応している場合も、LINE公式アカウントでは担当者を切り替えても会話履歴を共有できます。これにより、顧客に同じ説明を繰り返させる手間を減らし、スムーズな体験を提供可能です。
さらに、営業時間外メッセージの自動設定を活用すれば、担当者がオフラインでも「サービスが止まっている」印象を与えません。結果的に、工数削減と顧客満足度向上を同時に実現できます。
👉 無料機能だけでも「即応性・データ管理・顧客体験」の3つをカバーできるのがLINE公式アカウントの魅力です。中小企業にとっては、まずこれらの標準機能から始め、効果を実感しながら次のステップ(API連携やAI活用)へと進むのが理想的なアプローチとなります。
2025年のカスタマーサポート5大トレンド
顧客対応の現場は、ここ数年で大きな転換期を迎えています。
日本の消費者は、特に「待たされること」「同じ説明を繰り返すこと」に強いストレスを感じる傾向があります。DX推進が叫ばれる中、カスタマーサポートの高度化は、もはや大企業だけの課題ではありません。
SuperOfficeのグローバル調査では、2024年における最大トレンドとして「AI & Automation」が挙げられ、58%のカスタマーサービス責任者が最重要テーマに位置づけています。この傾向は日本でも同様で、顧客対応の高度化が喫緊の課題となっています。
ここでは、2025年以降に注目すべき5大トレンドを整理し、LINEを活用することでどのように実現できるのかを見ていきましょう。
![[JP] LINE Customer Service Localization](https://blog.cresclab.com/hs-fs/hubfs/%5BJP%5D%20LINE%20Customer%20Service%20Localization%20.jpg?width=1674&height=968&name=%5BJP%5D%20LINE%20Customer%20Service%20Localization%20.jpg)
① AI & 自動化:人的リソースの限界を超える
問い合わせ対応において、最も負担が大きいのは「繰り返される定型質問」です。AIと自動化を活用すれば、FAQ応答や簡易予約、注文確認などをボットが即時対応し、スタッフは複雑なケースに集中できます。
特にLINEでは、キーワード応答 × AIアシスト × 自動アサインの組み合わせで初回応答を高速化できます。Salesforceの最新データでも、セルフサービスやAIチャットボットの採用は高業績組織ほど進んでいると示されています。
② セルフサービス:顧客が自ら解決する時代
今日の消費者は、問い合わせ前に「自分で解決したい」傾向が強まっています。Salesforceによれば、61%の顧客は“シンプルな課題はセルフサービスで解決したい”と回答。LINEのリッチメニュー/FAQ自動応答整備は、自己解決率の向上と有人対応の負荷軽減に直結します。
LINEでは、リッチメニューやFAQ自動応答を整備することで、顧客は必要な情報にワンタップでアクセス可能です。これにより、自己解決率の上昇と、サポート負担の削減を同時に実現できます。
③ プロアクティブ通知:問い合わせを“待たない”サポート
従来のカスタマーサポートは「顧客からの連絡を待つ」スタイルでした。しかし今は、受け身のサポートから一歩進み、先回りの“プロアクティブ”対応へ。Microsoftの「Global State of Customer Service」では、世界の約3分の2の顧客が“プロアクティブ通知を好意的に評価”と報告。注文状況通知や未決済カートの自動リマインドは、CSAT向上と離脱防止に効きます。
LINEでは、注文状況通知・来店リマインド・未決済カートのお知らせなどを自動配信でき、顧客が不安や不満を抱く前にケアできます。結果として、顧客満足度(CSAT)の向上と離脱防止につながるのです。
④ パーソナライズ対応:一人ひとりに合わせた体験
顧客はもはや「一律の対応」では満足しません。購買履歴や行動データをもとに、最適なタイミングで最適なメッセージを届けることが求められています。SuperOfficeや各社のCXレポートでも、個別化が主要トレンドとして継続的に挙がる一方、Zendesk/Salesforce系の統計では“良い体験が再購入や収益に直結”することが示されています。
LINE公式アカウントにタグやセグメント機能を組み合わせれば、VIP顧客には優先サポート、リピーターにはおすすめ商品クーポンといったパーソナライズ体験を実現可能です。結果的に、顧客ロイヤリティの強化とLTV向上につながります。
⑤ オムニチャネル連携:体験を分断しない
顧客の購買行動は、オンラインとオフライン、SNSと店舗を自在に行き来します。強いオムニチャネルは平均89%の顧客を維持し、弱い場合は33%に留まるというデータもあります。
この課題に対し、LINEはFacebook Messenger・Instagram・電話・メールとの連携を可能にし、CAACを活用すれば複数チャネルの問い合わせを一元管理できます。「どのチャネルから問い合わせても同じ体験が得られる」ことは、2025年以降の競争優位を左右する重要なポイントです。
👉 この5大トレンドを踏まえると、LINEでのお問い合わせ対応は単なる効率化ツールに留まりません。AI・自動化・パーソナライズ・オムニチャネル戦略を組み込むことで、企業は顧客体験を武器にできるのです。
参考文献:
-
SuperOffice「Customer Service Trends 2024」SuperOffice
-
Salesforce「State of Service / Customer service stats」 Salesforce
-
Microsoft「Global State of Customer Service」 Microsoft Marketing Assets+1
-
UniformMarket「Must Know Omnichannel Statistics For Marketers (2025)」 UniformMarket
MAAC・CAACで実現:頭一つ抜き出たLINEお問い合わせ対応
ここまで見てきたように、LINE公式アカウントの標準機能や基本的な自動化だけでも、十分に顧客対応を効率化できます。ですが、企業規模が拡大し、問い合わせ件数や顧客の期待値が高まると、「もっと高度な仕組みが必要だ」と感じる瞬間が必ず訪れます。
そこで役立つのが、クレッシェンドラボが提供するMAAC(Messaging Analytics & Automation Cloud)とCAAC(Conversation Analytics & Automation Cloud)です。単なる拡張ツールではなく、問い合わせ対応を“次のレベル”へ押し上げるプラットフォームとして機能します。
CAAC:問い合わせ対応の効率化と品質向上
CAACは「問い合わせ対応そのもの」を高度化するプラットフォームです。

自動アサイン機能:
- キーワード検知で専門担当者に自動振り分け
- 「返品」→返品担当、「技術的な質問」→技術サポート
- 応答スピードと専門性を同時に向上
AI応答支援:
- 過去の類似問い合わせからAIが返信候補を提示
- 対応時間を50%短縮
- 新人スタッフでも品質の高い対応が可能
複数アカウント一元管理:
- 店舗別・部門別アカウントの履歴を統合
- 顧客がどの窓口から問い合わせても全履歴を参照可能
- 「前回も同じこと聞きました」を防止
VIP顧客の優先対応:
- 重要顧客を自動検知してエスカレーション
- 大口案件も見逃さない
これにより、複雑なケースや高付加価値な顧客にも、スピーディかつ的確な対応が可能になります。結果として、一次解決率(FCR)やCSATが向上し、担当者の負担も軽減されます。CAACに関する詳しい記事はこちら>複数LINE公式アカウントの管理方法|CAACで一元化&効率UP!
MAAC:問い合わせデータの活用と予防
MAACは、問い合わせ対応で得たデータを分析・活用し、問い合わせ自体を減らす仕組みを提供します。
-Feb-26-2025-05-46-01-4039-AM.webp?width=800&height=484&name=62d785516bb311497df144a0_MAAC-product-Hero-p-800%20(1)-Feb-26-2025-05-46-01-4039-AM.webp)
問い合わせ分析:
- どの質問が多いかを自動集計
- FAQの優先順位を最適化
- 「配送」問い合わせが急増 → FAQを強化
顧客理解の深化:
- 問い合わせ履歴を自動タグ化
- 次回問い合わせ時に過去の文脈を即座に把握
- 「以前〇〇について質問された方ですね」と即応
プロアクティブサポート:
- よくある問題を先回りして情報発信
- 例:「この商品を買った人がよく聞く質問」を購入後自動配信
- 問い合わせ前に解決 → 顧客満足度向上
外部データ連携:
- GA4:Webサイトでの行動を把握
- CRM:過去の購買履歴・対応履歴を統合
- ECサイト:注文状況・配送状況と連携
MAACでさらに可能になるお役立ち機能:
- セグメント配信:顧客の属性や行動に応じて、自動的にメッセージを最適化。例:商品ページを閲覧した顧客にだけ、24時間以内にクーポンを配信。
- パーソナライズ通知:GA4との連携により、過去の購買履歴や閲覧履歴に基づいた提案が可能。
- 配信タイミングの最適化:顧客が最も反応しやすい時間帯を自動分析し、開封率やクリック率を最大化。
つまり、MAACを導入することで、「お問い合わせ対応」が単なるサポートから、LTVを押し上げるマーケティング施策へと進化します。
MAAC × CAAC:問い合わせ対応を“武器”に変える
MAACとCAACは、それぞれが強みを持ちながら、組み合わせることで最大の効果を発揮します。

例えば、返品に関する問い合わせが届いた場合:
- MAACが自動応答で基本的な返金ポリシーを提示。
- 内容が複雑ならCAACが担当者に振り分け、AIが返信候補を支援。
- 対応完了後はMAACがアンケート配信や次回購入クーポンを自動送信。
この流れによって、顧客の疑問解決 → 信頼獲得 → 再購入促進まで、すべてをLINEの中で完結できます。まさに、「お問い合わせ対応」から「顧客体験設計」へと進化するのです。
よくある課題と解決策
Q1. 複数のLINE公式アカウントで顧客データが分散してしまう…
A. 部門や拠点ごとにLINE公式アカウントを運用すると、顧客情報がバラバラになり「誰が何を対応したのか」が見えにくくなります。これでは顧客に同じ説明を繰り返させたり、サポートの一貫性が失われたりしかねません。
解決策は「集中管理」です。 CAACを導入すれば、複数アカウントの履歴やタグを一元化でき、どの窓口から問い合わせても顧客の全履歴を参照できます。結果的に、スムーズな体験と効率的な運営が両立します。
Q2. FAQを作ったのに、問い合わせ件数がなかなか減らない…
A. FAQページを用意しても、顧客が探しにくかったり、LINEの中でアクセスできなかったりすると、効果は限定的です。
解決策は「FAQをLINE内に組み込むこと」です。
リッチメニューやキーワード応答を活用して、FAQへの導線を直感的に配置すれば、顧客はワンタップで自己解決できます。さらに、難しい質問だけを有人対応に切り替えるハイブリッド設計にすれば、自己解決率を高めながらCSATを維持できます。
Q3. メッセージ配信が多すぎてブロック率が上がってしまう...
A. 問い合わせ対応を起点に情報を配信していると、つい通知が増えがちです。その結果「しつこい」と感じられ、ブロック率が上がってしまうことも。
解決策は「セグメント化と配信頻度の最適化」です。
MAACを使えば、特定の商品に興味を示した顧客にだけ関連情報を届けることができ、不要な通知を避けられます。さらに、配信回数を制御するルールを設定することで、必要な情報だけが届く快適な体験を提供できます。
Q4. 小規模事業者でもLINEお問い合わせ対応を導入できますか?
A. はい、むしろ小規模事業者こそLINEが最適です。初期費用ゼロで始められ、LINE公式アカウントの無料プランでも月1,000通までメッセージを送信可能。まずは応答メッセージとリッチメニューの設定から始め、効果を見ながら段階的に機能を追加していけば、無理なく運用できます。
Q5. 応答メッセージとチャットボットの違いは?
A. 応答メッセージはLINE公式アカウントの標準機能で、簡単に設定できる基本的な自動返信です。一方、チャットボット(特にMessaging API活用)は、より複雑なシナリオ分岐、データ連携、パーソナライズが可能な高度な自動化です。
Q6. 自動応答だけだと冷たい印象になりませんか?
A. 確かに、すべてを自動化すると機械的な印象を与える可能性があります。そこで推奨するのが「ハイブリッド対応」です。
バランスの取り方:
簡単な質問(営業時間・料金)→ 自動応答複雑な相談・クレーム → 有人対応自動応答の最後に「解決しない場合は担当者に相談」ボタンを設置
この組み合わせで、効率と温かみを両立できます。
Q7. 設定した自動応答が反応しないのですが?
A. よくある原因と対処法:
原因1:キーワードが完全一致になっている
対処法:表記ゆれを全て登録(「営業時間」「営業じかん」「何時まで」等)
原因2:応答モードが「チャット」になっている対処法:「チャット+応答メッセージ」に変更
原因3:スペースや記号が入っている
対処法:シンプルなキーワードに変更
原因4:優先順位の問題
対処法:より具体的なキーワードを上位に設定
Q8. 問い合わせ対応の効果測定はどうすればいい?
A. 以下の指標をモニタリングしましょう:
効率指標:
- 自動応答率(全体の何%が自動で解決したか)
- 平均対応時間(問い合わせから完了まで
- 有人対応件数(月次推移)
満足度指標:
- ブロック率(15%以下が目標)
- アンケート満足度(CSAT)
- リピート問い合わせ率
ビジネス指標:
- 問い合わせ経由のCV率問い合わせコスト(1件あたり)
- LTV(顧客生涯価値)
LINE公式アカウントの分析機能やMAACの詳細レポートを活用して、定期的に効果を測定し、改善サイクルを回しましょう。
成功事例
1) Zuyou:CAACでLINE公式アカウント管理を効率化し、応答時間を大幅短縮
台湾を拠点とする「Zuyou」は、デジタル技術を活用して住宅管理と賃貸サービスを効率化するブランドです。Zuyouではセルフメディアを活用し、正しい賃貸の概念や知識を広めながら、伝統的な不動産市場に新たな価値を提供することを目指しています。その取り組みの一環として、デジタル化とテクノロジーの融合による革新を推進しています。
導入前、「Zuyou」は4つの異なるLINE公式アカウントを使用してサービスを提供していました。しかし、複数アカウントの運用は以下のような課題を抱えていました:
- メッセージ管理の煩雑さ: 各アカウントに分散した顧客メッセージが一元管理できず、対応の遅れや混乱が発生。
- 非効率的なリソース配分: チーム間での情報共有や担当割り振りが非効率的。
- 顧客体験の低下: メッセージ返信の遅延や重複対応が、顧客満足度に悪影響を与える可能性。
 CAACを導入することで、4つのアカウントを1つに統合し、自動割り当て機能やAIアシスタントを活用した柔軟なチーム運営を実現。結果として、メッセージの応答速度が6倍に向上し、効率的な業務運営と顧客満足度の向上を両立しました。
CAACを導入することで、4つのアカウントを1つに統合し、自動割り当て機能やAIアシスタントを活用した柔軟なチーム運営を実現。結果として、メッセージの応答速度が6倍に向上し、効率的な業務運営と顧客満足度の向上を両立しました。
CAACは「Zuyou」のデジタル戦略を支える重要なツールとなり、顧客体験を大きく進化させる成功事例となっています。住宅管理や賃貸業務を効率化したい企業にとって、Zuyouの成功事例は非常に参考になります。
2) 多慶屋:顧客を夢中にさせるMAAC「ゲーム機能」で、聞かれる前に応えるプロアクティブ対応を実現!
食品から医薬品、ファッション、リフォームまで多様な商品を扱う多慶屋では、LINE公式アカウントを単なる「問い合わせ窓口」ではなく、顧客関係を深める接点として活用しています。
▼導入前の課題
多慶屋では、顧客一人ひとりの興味が多岐にわたるため、 お問い合わせ内容も幅広く、さらに一斉配信では「誰にも響かない」 メッセージになりがちでした。顧客の関心を惹きつけ、 アクティブに関わることで顧客を深く知ることが求められていました。
そこで導入されたのが、MAACの「パーソナライズ×ゲーム機能」によるプロアクティブ戦略。多慶屋では、MAAC のゲーム機能を積極的に導入し、顧客が楽しみながらブランドと接触する機会を創出。 顧客とのアクティブなインタラクションで得られた情報を「タグ」に変換、顧客の興味・関心や属性を詳細に分類しています。

▼導入施策:
- 顧客の興味に合わせた「特別オファー」: MAACの柔軟な「タグ」システムを活用し、顧客の興味・属性を細かく分類。これにより、顧客一人ひとりに最適化された情報提供を実現しました。
- 「ゲーム機能」による能動的エンゲージメント: 顧客が「わくわく」するようなルーレットやガチャなどのゲーム機能をLINE上で提供。これにより、顧客は楽しみながら能動的にブランドと関わるようになりました。
- 行動データに基づく自動フォローアップ: ゲームの結果に応じて顧客に「タグ」を付与し、「当選者には景品引換案内」、「未当選者には再挑戦クーポン」といったパーソナライズされたメッセージを自動配信。これにより、顧客を飽きさせずに次の行動へと導きました。
▼導入後の成果

→ 高いタグ保有率と安定したオープン率は、MAAC によるきめ細やかなパーソナライズと、「楽しい!」を引き出すゲーム機能が成功している証です。MAAC は、ユーザーの興味・属性を細かく「タグ」で分類し、ターゲットに最適化された「聞かれる前に答える」メッセージ配信を可能にします。加えて、すぐに導入できるゲーミフィケーション機能が、顧客の心を掴み、長期的な関係構築をパワフルにサポートします。
このように、LINEを通じた問い合わせ対応は、単に「効率化のため」ではなく、顧客体験の質を高め、売上やロイヤリティを押し上げる経営戦略の一部として機能していきます。
詳しい活用例、事例はこちら>脱とりあえず一斉配信 LINEでのセグメンテーションをより高度に、効果的に
まとめ
LINEは日本国内で9,800万人が利用する「生活インフラ」であり、お問い合わせ対応の第一チャネルとして最適です。
本記事でご紹介した通り:
✓ 無料機能だけでも十分な効果が期待できる
- 応答メッセージ、タグ付け、リッチメニューで基本的な自動化が可能
✓ AI・自動化・パーソナライズで顧客体験が劇的に向上
- 2025年の5大トレンドを押さえることで競争優位を確立
✓ MAAC/CAACを活用すれば、問い合わせ対応がLTV向上の起点に
- 単なるサポートから、マーケティング施策へと進化
まずは小さく始めて、段階的に高度化していく——それが成功への最短ルートです。顧客が最も使いやすいチャネルで、最高の体験を提供しましょう。
自動化・有人切替・データ活用を組み合わせてCS効率と顧客体験を両立させることで、LINEは「顧客対応をDX化し、顧客体験を武器に変える」強力なプラットフォームとなります。
Kokoro Tomita
JP Content Writer, Crescendo Lab, Taiwan

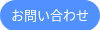

.png?width=837&height=484&name=JP%20Blog%20Featured%20Image%20(18).png)

.png?width=284&height=165&name=JP%20Blog%20Featured%20Image%20(19).png)
-Nov-25-2025-08-18-47-3973-AM.png?width=284&height=165&name=JP%20Blog%20Featured%20Image%20(1)-Nov-25-2025-08-18-47-3973-AM.png)
.png?width=284&height=165&name=JP%20Blog%20Featured%20Image%20(17).png)