目次
1. はじめに
日本におけるLINEの月間アクティブユーザー数は9,800万人(2025年時点、LINEヤフー株式会社発表)を超え、もはや国民的インフラとなっています。多くの企業が公式アカウントを運用し、顧客との接点強化を図る一方で、
-
「友だちは増えるが、リピーターが増えない」
-
「メッセージを送っても開封されない」
-
「ブロック率が高い」
といった課題に直面しています。その大きな要因が「顧客の飽き」と「メッセージ疲れ」。そこでクレッシェンドラボが提案するのがゲーム機能を使った「飽きさせない体験」の導入です。
%20(9).png?width=1200&height=627&name=Copy%20of%20Blog%20Design%20Templates%20(by%20Belinda)%20(9).png)
本記事では、「とりあえず一斉配信から脱却」し、LINE公式アカウントで顧客の心を動かしリピーターへと育成する「飽きさせない体験設計」を徹底解説します。今日から実践できる具体的な戦略で、LINEマーケティングを次のステージへと引き上げ、LTV(顧客生涯価値)を最大化しましょう。
>より詳細な「脱とりあえず配信」の戦略・事例はこちらからダウンロード
2. 課題:なぜリピーター増加が難しいのか?市場と文化背景を分析
現在のLINE市場の課題
LINE公式アカウントを運用する多くの企業が抱える共通の悩み——それは「最初は友だちが増えるが、いつの間にかエンゲージメントが下がっていく」という現象です。 実はこの現象には、現在のLINE市場特有の構造的な問題と、日本の消費者心理が深く関わっています。なぜ顧客は離れていくのか、その根本原因を3つの角度から分析してみましょう。

-
メッセージ疲労(Message Fatigue): 多くの企業がLINE公式アカウントを開設した結果、ユーザーは日々、過剰なプロモーションメッセージに晒されています。これにより、「また広告か」「自分には関係ない」と感じ、メッセージを読み飛ばしたり、最終的にはブロックしたりする「メッセージ疲労」が深刻化。
-
プラットフォームの飽和: 企業アカウントの増加は、同時にユーザーのタイムラインにおけるメッセージの「競争」を意味します。数あるメッセージの中から自社のものが選ばれ、読まれるためには、単なる情報配信以上の工夫が必要に。
- 日本特有の文化背景:71%の日本人消費者がパーソナライズされた体験を期待。画一的な対応や無関係な情報には敏感で、不満や離反に繋がりやすい傾向があります。さらに、日本の顧客は過度なプッシュを嫌う傾向。ユーザーが自ら関わりたくなる“非干渉型”の接点を継続的に設けることが重要です。出典:Adobe. (2024). Digital Trends 2024: Japan.
つまり、LINEはもはや単なる情報伝達ツールでではなく、顧客の心に響く「体験」を提供できるかどうかが、リピーター育成の成否を分ける時代になっているのです。
3. 解決策:「タグ×ゲーム×自動化」の3要素で「飽きさせない体験」を設計する
課題が明確になったところで、ここからが本題です。 前章で見てきた3つの壁——メッセージ疲労、プラットフォーム飽和、日本特有の文化背景——を乗り越え、リピーター育成を実現する鍵となるのが、顧客の記憶に残る体験と関係作り。それを可能にするのが、クレッシェンドラボが提案する「タグ」「ゲーム」「自動化」の3つの要素を組み合わせた「飽きさせない体験設計」です。

この3つの組み合わせが① 顧客を深く理解し ②楽しい体験を提供し ③最適なタイミングで関わるアプローチを実現します。以下ではこの3要素の役割を一つ一つ紐解いていきます。
要素1:タグ(高精度パーソナライズ)
まず最初の要素は「顧客を深く知る」ことから始まります。

1)仕組み:顧客の興味・関心、行動履歴、属性を細かく「タグ」で自動分類・蓄積。
2)解決する課題:
- 手軽さゆえの一斉配信は『自分向けでない情報』と受け取られ、ブロック増加の大きな要因に。
- 来店や購入にとどまる“結果”データだけでは、深い顧客インサイトを得ることができず、的外れなコミュニケーションに陥りがち。
3)効果: 細かい自動タグ付けにより、単なる「20代女性」ではなく、「20代女性×コスメ好き×セール情報重視×過去3ヶ月に未購入」といった、多層的な理解・セグメント配信が可能になります。これによて顧客は「自分のことを理解してくれている」と感じ、愛着やロイヤリティを育み、ブロック率の大幅低下に繋がっていきます。
要素2:ゲーム(能動的エンゲージメント)
顧客の詳細な情報が揃ったら、次は「飽きさせない」にアプローチする「感情を動かす体験」を提供します。

1)仕組み: ルーレットやクイズなど、顧客が「楽しい」「面白い」「自分も参加したい」と感じるインタラクティブな仕掛けをLINE上で提供。>より詳しいMAACのゲーム機能についてはこちら
2)解決する課題:
- 機能的価値情報中心では感情が揺さぶられず、顧客はすぐに飽きてしまう。
- 単調な情報配信では顧客を「受け手」に留めてしまい、ブランドとの双方向的かつ継続的なつながりが生まれない。
3)効果:能動的な参加によって体験がポジティブな記憶として定着し、リピート来店の強力な動機付けに。また、遊びを通じて顧客が自然と関わることで、ブランドへの「特別感」が醸成されます。
→ ゲームで顧客の心を掴むことができても、その後のフォローが手動では限界があります。ここで真価を発揮するのが3つ目の要素「自動化」です。
要素3:自動化(効率的な育成サイクル)
最後の要素は、獲得した顧客データとエンゲージメントを「持続可能な関係」に発展させる仕組みです。

1)仕組み: MAACスマート配信は、タグや行動データをトリガーにして、最適なメッセージを最適なタイミングを分析し自動配信。
2)解決する課題:
- 手動フォローアップでは顧客行動に応じた最適なタイミングを逃し、離脱や機会損失を招く。
- 顧客の忙しいタイミング・LINEをチェックしないタイミングで送信してしまい「煩わしさ」を感じさてしまう。
3)効果: 例えば、ゲーム参加者には即座に結果と特典を、未参加者には3日後にリマインドを、といった複雑なシナリオも自動実行できます。これにより、24時間365日、顧客一人ひとりの行動に寄り添った「ちょうどいい」コミュニケーションが実現し、運用負荷を削減しながら顧客満足度を向上させます。
これら3つの要素を組み合わせることで、顧客は「受け手」ではなく「参加者」としてブランドに関わり、自らのポジティブな体験として記憶に刻まれる——まさに“飽きさせない体験設計”が可能になります。
導入のハードルは想像以上に低い!
「複雑そう」「運用が大変では?」という懸念は不要です。MAACなら:
①ノーコードで直感的操作:プログラミング知識不要
② 豊富なテンプレート:すぐに使えるゲームやシナリオを用意
③ 段階的な導入が可能:まずはゲーム機能だけ、といったスモールスタートもOK
4. 実践ステップ:MAACで実現する「飽きさせない体験設計」5ステップ
理論は理解できたけれど、実際にどこから始めればいいの? そんな疑問にお答えするため、ここではLINE公式アカウントを「飽きさせない」リピーター育成チャネルへと進化させるための具体的な実践5ステップを解説します。
Step 1: 顧客プロファイリングと「タグ」設計:誰に、何を届けたいかを明確化
顧客を「飽きさせない」ためには、まず顧客を深く理解することが不可欠です。MAACの柔軟な「タグ」システムを活用し、顧客の興味・関心、行動履歴、属性を細かく分類します。
このステップでできること
顧客を性別、年代、購入履歴、ウェブサイト閲覧履歴、メッセージ反応など多角的に分析し、それぞれの顧客セグメントに適切なタグを設定します。これにより、「全員に同じメッセージを送る」という一斉送信から脱却し、顧客一人ひとりに響くパーソナライズの基盤を築きます。
例
「コーヒー好き」「新規来店者(過去30日以内)」「特定商品購入者」「ゲームA参加済み」「リッチメニュー『商品一覧』クリック」など、顧客の行動や状態に合わせて多種多様なタグを設定できます。
チェックリスト
✓ 顧客のセグメントを洗い出し
✓ 各セグメントに対応するタグを具体的に設定
✓ 既存の顧客データ(CRMデータなど)と連携し、タグ付けを自動化できるか検討
Step 2: 「特別オファー」の企画とパーソナライズメッセージ:顧客の心を掴む第一歩
設定した「タグ」に基づき、顧客一人ひとりの興味に合わせた「特別感」のあるコンテンツやオファーを企画し、メッセージとして届けます。
このステップでできること
例えば、「食品好き」とタグ付けされた顧客には新着食材情報やレシピ、「ファッション好き」には最新トレンドやセールのお知らせ、といったように、顧客が「自分にぴったりの情報だ」と感じるようなメッセージを作成。これにより、メッセージの開封率を高め、顧客の期待感を醸成します。
例
「〇〇をお探しですか?夏限定の特別セールを今すぐチェック!」
「【会員様限定】新作アパレル20%OFFクーポン!」
「【未利用のあなたへ】初回限定〇〇体験クーポン」
チェックリスト
✓ 顧客が「自分向けだ」と感じるような表現(例:顧客名差し込み)を意識
✓ 特典や情報の受け取り方が明確で、スムーズな導線設計ができている
Step 3: 「ゲーム機能」の導入と「行動データ」の取得:楽しみながら顧客を深く知る
ここが「飽きさせない体験設計」の核心です。MAACのゲーム機能を活用し、顧客が思わず参加したくなる「遊び」を提供。その参加を通じて、顧客の興味や行動に関する貴重なデータを自動で取得します。
このステップでできること
ルーレット、ガチャ、クイズ、スロットなど、顧客が能動的に楽しめるインタラクティブなゲームをLINE上で展開します。顧客は「楽しい」と感じながらゲームに参加し、その結果や選択に応じて、裏側でMAACが自動的に新たな「タグ」を付与します。これにより、メッセージ開封・クリックといった表面的なデータだけでなく、「何のゲームに参加したか」「ゲームの結果はどうだったか」「何に興味を示したか」といった、より深い顧客インサイトを獲得できます。
例
「今日の運試し!ルーレットを回して限定クーポンをゲット!」(参加で「ルーレット参加済み」タグ付与)
「あなたの興味はどれ?クイズに答えておすすめ商品診断」(回答内容に応じて「〇〇興味」タグ付与)
ゲームの結果に応じて「当たりタグ」「ハズレタグ」などを付与し、次のステップへ誘導
チェックリスト
✓ どのようなゲーム機能が顧客に響くか、ターゲット層の特性を踏まえて検討
✓ ゲーム参加で得られるデータ(タグ)の設計は、その後のシナリオ設計に役立つものになっている
✓ 参加ハードルを低く設定し、誰もが気軽に楽しめるような工夫
Step 4: 「自動シナリオ」構築と「顧客育成」フロー:行動に応じた最適なフォローアップ
ゲームで得られた顧客の行動データ(タグ)を元に、MAACの自動化機能を活用して、顧客への最適な次のアクションをタイムリーに配信します。これにより、顧客を飽きさせずに、次のステップへとスムーズに誘導し、LTV向上へと繋げます。
このステップでできること
例えば、ゲームで「当たり」が出た顧客には来店を促すメッセージと景品引換案内を自動で配信。「ハズレ」た顧客には、再挑戦クーポンや次回のおすすめ商品情報を送ることで、離脱を防ぎ、継続的なエンゲージメントを促します。また、「特定の商品ページを閲覧した」タグを持つ顧客には、その商品の詳細情報や関連アイテムを提案するなど、顧客の興味が最も高い瞬間にアプローチできます。これにより、手動では不可能なパーソナライズされた、きめ細やかな顧客育成が可能になります。
例
購入検討層向け: 「〇〇商品を見てくださったあなたへ。今だけ限定!お試しサンプルプレゼント」
来店促進: 「【ゲーム当たり!】今すぐ店舗で引き換え!限定ノベルティのご案内」
離反防止: 「久しぶりのあなたに、特別な〇〇クーポンをご用意しました」
チェックリスト
✓ 顧客の行動パターン(タグ)に応じた複数の自動配信シナリオを設計
✓ 各シナリオで配信するメッセージ内容、タイミング、配信形式(リッチメッセージ、動画など)を決定
✓ シナリオが顧客の「飽き」を防ぎ、次の行動へとスムーズに繋がるような導線を設計
Step 5: 効果測定と改善サイクル:データで裏付けられたPDCA
「飽きさせない体験設計」は一度作って終わりではありません。MAACの提供する詳細な分析機能を使って、配信結果(開封率、クリック率、ゲーム参加率、コンバージョン率、ブロック率など)を継続的に測定し、改善サイクルを回すことが重要です。
このステップでできること
: どのメッセージが最も開封されたか、どのゲームの参加率が高いか、ブロック率に変化はないかなどをMAACの管理画面で詳細に分析します。このデータに基づき、タグ設計の見直し、メッセージ内容の調整、ゲームのバリエーション追加、シナリオの改善などを行い、より効果的な「飽きさせない体験」を追求していきます。PDCAサイクルを回すことで、常に顧客のニーズに合致した最適なコミュニケーションを実現し、リピーターの定着を加速させます。
例
「特定セグメントのブロック率が高い」→ メッセージ頻度を調整するか、コンテンツ内容を見直す。
「特定のゲームの参加率が低い」→ ゲーム内容や告知方法を改善するか、別のゲームを試す。
「クーポン利用率が低い」→ 顧客へのインセンティブ設計やクーポンの告知方法を再検討する。
チェックリスト
✓ 主要なKPI(重要業績評価指標)を明確に設定
✓ 定期的に効果測定と分析を行っている
✓ 分析結果に基づき、具体的な改善策を立案し実行
5. 成功事例:顧客を夢中にさせる「ゲーム機能」で、ブロック率 11%タグ保有率 89% を実現!
▼導入前の「もったいない」
食品から医薬品、ファッション、リフォームまで多様な商品を扱う多慶屋では、顧客一人ひとりの興味が多岐にわたるため、 一斉配信では「誰にも響かない」 メッセージになりがちでした。顧客の関心を惹きつけ、 来店や購入を促す新しい仕掛けが求められていました。
そこで導入されたのが、MAACの「パーソナライズ×ゲーム機能」でした。多慶屋では、MAAC の柔軟な「タグ」システムを活用し、顧客の興味・関心や属性を詳細に分類。さらに、MAAC のゲーム機能を積極的に導入し、顧客が楽しみながらブランドと接触する機会を創出しています。

▼導入施策:
- 顧客の興味に合わせた「特別オファー」: MAACの柔軟な「タグ」システムを活用し、顧客の興味・属性を細かく分類。これにより、顧客一人ひとりに最適化されたメッセージ配信を実現しました
- 「ゲーム機能」による能動的エンゲージメント: 顧客が「わくわく」するようなルーレットやガチャなどのゲーム機能をLINE上で提供。これにより、顧客は楽しみながら能動的にブランドと関わるようになりました。
- 行動データに基づく自動フォローアップ: ゲームの結果に応じて顧客に「タグ」を付与し、「当選者には景品引換案内」、「未当選者には再挑戦クーポン」といったパーソナライズされたメッセージを自動配信。これにより、顧客を飽きさせずに次の行動へと導きました。
▼導入後の成果

→ 高いタグ保有率と安定したオープン率は、MAAC によるきめ細やかなパーソナライズと、「楽しい!」を引き出すゲーム機能が成功している証です。顧客が自ら進んで LINE と関わる仕組みを構築しました。MAAC は、ユーザーの興味・属性を細かく「タグ」で分類し、ターゲットに最適化されたメッセージ配信を可能にします。加えて、すぐに導入できるゲーミフィケーション機能が、顧客の心を掴み、長期的な関係構築をパワフルにサポートします。
6. よくある質問(FAQ)
LINE公式アカウント活用やMAAC導入に関して、読者の皆様が抱きやすい疑問にお答えします。
Q1: LINE公式アカウントでリピーターを増やすには何が一番重要ですか?
A: 最も重要なのは、顧客を「飽きさせない体験設計」と「パーソナライズ」です。一方的な情報配信ではなく、顧客一人ひとりの興味関心に合わせた「楽しい・惹かれる」体験を提供し、継続的な関係性を築くことが鍵となります。
Q2: MAACの「ゲーム機能」はどのような業種でも効果がありますか?
A: はい、小売業、飲食業、サービス業、ECサイト運営など、顧客との継続的な接点が必要な幅広い業種で効果を発揮します。顧客エンゲージメントの向上、来店頻度や購入単価の増加に有効です。
Q3: MAACを導入するには専門知識が必要ですか?
A3: MAACはノーコードでの直感的な操作性を追求しており、プログラミングなどの専門知識がなくても簡単に導入・運用が可能です。専任の担当者による丁寧なサポート体制も充実しているため、安心してご利用いただけます。
Q4: 既存のLINE公式アカウントからMAACへの移行はスムーズにできますか?
A: はい、既存のLINE公式アカウントの友だち情報や設定をMAACに連携し、スムーズに移行できるようサポートいたします。LINE以外からのデータ移行や設定に柔軟に対応させていただけるのもMAACの強みです。
Q5: ブロック率を低く保つための秘訣は何ですか?
A: ブロック率を低く保つためには、顧客の興味に合わせたパーソナライズ配信を徹底し、メッセージ頻度を最適化することが重要です。また、MAACのゲーム機能のように、顧客が「楽しい」「面白い」と感じる体験を提供することで、アカウントの価値を高め、ブロックされる要因を減らすことができます。
7. まとめ
本記事では、LINEリピーターを増やすための鍵が、顧客を「飽きさせない体験設計」にあることをご紹介しました。多くの企業が直面する「メッセージ疲れ」や「パーソナライズ不足」といった課題に対し、MAACの「タグ」「ゲーム」「自動化」という3つの要素の組み合わせが、顧客一人ひとりに合わせた「特別な体験」を実現します。
多慶屋様の成功事例が示すように、MAACを導入することで、ブロック率の低下、タグ保有率の向上、そして最終的なリピーター増加へと繋がる具体的な成果が期待できます。ぜひ本記事でご紹介した「飽きさせない体験設計」を実践し、ビジネスのLTVを最大化してください。
Kokoro Tomita
JP Content Writer, Crescendo Lab, Taiwan

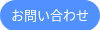

.png?width=837&height=484&name=JP%20Blog%20Featured%20Image%20(17).png)

.png?width=284&height=165&name=JP%20Blog%20Featured%20Image%20(19).png)
-Nov-25-2025-08-18-47-3973-AM.png?width=284&height=165&name=JP%20Blog%20Featured%20Image%20(1)-Nov-25-2025-08-18-47-3973-AM.png)
.png?width=284&height=165&name=JP%20Blog%20Featured%20Image%20(18).png)